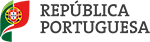アルガルヴェ大学(UAlg)は、6月26日と27日に大阪・関西万博のポルトガル館で革新的な取り組みを発表しました。それは、日本のビジュアル美学にインスパイアされた、科学・アート・異文化対話を融合させたアニメーション映像です。
この映像は、UAlgの企業アクセラレーター「UAlg TEC Campus」から誕生したスタジオ「Fly Moustache」が制作しました。物語の主人公はフォルモーザ潟に生息するタツノオトシゴで、彼がこのユニークな生態系と、UAlgが進める研究プロジェクトを紹介します。作品はアニメやマンガのビジュアル世界を讃えるものであり、同時にポルトガル沿岸でこの種が減少している現実に対する静かな警鐘でもあります。
アルガルヴェ大学学長室長の アンドレ・ボテリェイロ 氏によると、日本のアニメーションを選んだのは偶然ではありません。
「科学機材や生きた生物を日本に持ち込むのは、物流面で不可能でした。私たちは、日本の観客に響く、インパクトのある何かが必要でした。アニメは日本での共通言語だと気づき、『彼らのやり方で私たちの物語を伝えたらどうだろう?』というアイデアが自然に生まれました。」
この映像は、UAlgの企業アクセラレーター「UAlg TEC Campus」から誕生したスタジオ「Fly Moustache」が制作しました。物語の主人公はフォルモーザ潟に生息するタツノオトシゴで、彼がこのユニークな生態系と、UAlgが進める研究プロジェクトを紹介します。作品はアニメやマンガのビジュアル世界を讃えるものであり、同時にポルトガル沿岸でこの種が減少している現実に対する静かな警鐘でもあります。
アルガルヴェ大学学長室長の アンドレ・ボテリェイロ 氏によると、日本のアニメーションを選んだのは偶然ではありません。
「科学機材や生きた生物を日本に持ち込むのは、物流面で不可能でした。私たちは、日本の観客に響く、インパクトのある何かが必要でした。アニメは日本での共通言語だと気づき、『彼らのやり方で私たちの物語を伝えたらどうだろう?』というアイデアが自然に生まれました。」

ポルトガル館のテーマ「海・青の対話」とのつながりは明白で、さらに幸運な偶然がこの結びつきを強めました。それは、ポルトガルの公式マスコット「ウミ」もタツノオトシゴだったのです。
「ウミがタツノオトシゴだと知ったとき、私たちのプロジェクトはすでにかなり進んでいました。これは幸運な偶然でした。万博のアイデンティティと、UAlgが数十年にわたりフォルモーザ潟で行ってきた科学研究の橋渡しを強化するのは、非常に意味があることでした」と アンドレ・ボテリェイロ 氏は語ります。
2000年当時、フォルモーザ潟は世界最大級のタツノオトシゴの生息地でした。しかしその後、この個体群は90%以上減少し、壊滅的な状況に陥っています。
「この現実を大げさにせず、静かに伝えたかったのです。この種の美しさ、象徴的な価値を示し、特にアジアからの来場者に意識してもらうことが目的でした」と アンドレ・ボテリェイロ 氏は付け加えます。
今回のアルガルヴェ大学の取り組みは、環境と科学だけでなく、次世代にもインスピレーションを与えています。初日のポルトガル館では、大阪在住の13歳の日本人少年、亀岡トマ君がアニメのタツノオトシゴを見て、フォルモーザ潟の自然を知り、そしてこう決めたのです。「まだ進学先は決めていませんが、今はポルトガルに行ってタツノオトシゴの研究をしたいと思っています」と彼は目を輝かせて話しました。
「ウミがタツノオトシゴだと知ったとき、私たちのプロジェクトはすでにかなり進んでいました。これは幸運な偶然でした。万博のアイデンティティと、UAlgが数十年にわたりフォルモーザ潟で行ってきた科学研究の橋渡しを強化するのは、非常に意味があることでした」と アンドレ・ボテリェイロ 氏は語ります。
2000年当時、フォルモーザ潟は世界最大級のタツノオトシゴの生息地でした。しかしその後、この個体群は90%以上減少し、壊滅的な状況に陥っています。
「この現実を大げさにせず、静かに伝えたかったのです。この種の美しさ、象徴的な価値を示し、特にアジアからの来場者に意識してもらうことが目的でした」と アンドレ・ボテリェイロ 氏は付け加えます。
今回のアルガルヴェ大学の取り組みは、環境と科学だけでなく、次世代にもインスピレーションを与えています。初日のポルトガル館では、大阪在住の13歳の日本人少年、亀岡トマ君がアニメのタツノオトシゴを見て、フォルモーザ潟の自然を知り、そしてこう決めたのです。「まだ進学先は決めていませんが、今はポルトガルに行ってタツノオトシゴの研究をしたいと思っています」と彼は目を輝かせて話しました。

アンドレ・ボテリェイロ 氏は、このような取り組みの本当の意義について次のように語ります。
「こうした活動は、架け橋を築き、ポルトガルの科学を世界に知らしめ、ポルトガルブランドを強化する手段です。明日、私たちが東京で日本の大学と会議をするとき、彼らは私たちのことを知っているでしょう。なぜなら、ここ、ポルトガル館で私たちを見たからです。」
アルガルヴェ大学の参加は、NERA(アルガルヴェ地域企業協会)が主導するプロジェクト「INTERNACIONALIZAR+ALGARVE 3.0」の一環であり、EUの資金提供を受けて、ALGARVE 2030プログラムの枠組み内で実施されています。
ポルトガルは、大阪・夢洲(ゆめしま)で開催中の大阪・関西万博に参加している160カ国の1つです。万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」で、会期は10月13日まで。これまでに1,000万人以上が来場し、ポルトガル館には4月13日の開館以来、70万人以上が訪れています。ポルトガル館では、企業、大学、自治体、協会、アーティストなど、150以上の団体が一体となり、海と共に歩むポルトガルの姿を世界に発信しています。
「こうした活動は、架け橋を築き、ポルトガルの科学を世界に知らしめ、ポルトガルブランドを強化する手段です。明日、私たちが東京で日本の大学と会議をするとき、彼らは私たちのことを知っているでしょう。なぜなら、ここ、ポルトガル館で私たちを見たからです。」
アルガルヴェ大学の参加は、NERA(アルガルヴェ地域企業協会)が主導するプロジェクト「INTERNACIONALIZAR+ALGARVE 3.0」の一環であり、EUの資金提供を受けて、ALGARVE 2030プログラムの枠組み内で実施されています。
ポルトガルは、大阪・夢洲(ゆめしま)で開催中の大阪・関西万博に参加している160カ国の1つです。万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」で、会期は10月13日まで。これまでに1,000万人以上が来場し、ポルトガル館には4月13日の開館以来、70万人以上が訪れています。ポルトガル館では、企業、大学、自治体、協会、アーティストなど、150以上の団体が一体となり、海と共に歩むポルトガルの姿を世界に発信しています。